| 事故類型 | 機械等の巻き込まれ・挟まれ |
|---|---|
| 職種 | クレーンオペレーター |
| 傷病名(症状) | 腰椎横突起骨折、背部挫傷 |
| 相談時の状況 | 治療中 |
| 年代 | 40代 |
| 勤務形態 | 正社員 |
| 被災した状況 | 事故当日、建設現場で大型クレーン車を操縦し、荷運びをしていた。クレーン車のロードセル(荷重測定器)は壊れていたので、安全装置のリミッター解除をしたまま操縦するという状況が常態化し、会社側はこれを黙認していた。リミッター解除をしてオーバーロード(過積載)状態になったまま、クレーン車で荷物をつり上げたところ、荷物の重さでクレーン車はバランスを崩して転覆し、被災した。 |
| ご相談者 | ご本人 |
相談内容
事故から3ヶ月ほど経ってお問合せいただきました。ご面談では以下のようなご質問をいただきました。
- 現在も治療を続けているが、後遺障害が残りそうだ。今後について相談したい。
- 会社側が労災申請をしてくれたものの、事実とは異なる内容で申請された。
- 会社からは本当のことは黙ってくれと言われているのだが、どうしたらいいか?
- 会社には長年勤めてきたので、賠償請求について迷っている。
弁護士からのアドバイス
後遺障害について
まず、お怪我の内容や現在の症状などをお伺いしました。その結果、後遺障害が残った場合、後遺障害等級12級もしくは14級程度が認定される可能性があることをご説明しました。
12級や14級というのは、いわゆる神経症状の後遺障害に対して認定される等級です。
万が一後遺障害が残ってしまった場合に備えて、今のうちから受けておくべき検査などをアドバイスしました。

事故態様について
①「労災かくし」について
「労災かくし」という言葉をご存じでしょうか。
事業者は、労働災害等により労働者が死亡又は休業した場合には、遅滞なく、労働者死傷病報告等を労働基準監督署長に提出しなければなりません。「労災かくし」とは、事業者が労災事故の発生をかくすため、労働者死傷病報告(労働安全衛生法第100条、労働安全衛生規則第97条)を、(1)故意に提出しないこと、(2)虚偽の内容を記載して提出することをいいます。
出典: 厚生労働省 労災かくしとは何ですか。
このように、「労災かくし」は、労災の発生を隠すことはもちろん、労災の内容を偽ること(隠すこと)も含まれます。 そして、この「労災かくし」は犯罪です。
参考:神奈川労働局「労災かくし」は犯罪です【労災補償課・労働保険徴収課】
②申請内容と事実の相違について
会社側からは、本当の事故原因や仕事を休んでいることなどは黙っていてほしい、と言われたそうですが、会社側の要請は「労災かくし」になる可能性もありうるものでした。会社側の要請に従っても事実と異なる証拠が残ってしまい、ご相談者が不利益を被るばかりです。そのため、ご相談者には、労基署へは事実をありのまま報告するようアドバイスいたしました。
損害賠償請求について
治療中の段階では、「勤務先へ損害賠償請求するかどうか迷っている」という方もいらっしゃいます。お怪我がどの程度治るかもわからない段階では、迷われるのも当然だと思います。休業補償などで当面の生活費の心配がない場合は、勤務先への損害賠償請求については保留にしたまま治療と労災申請の準備に専念していくこともひとつの選択肢です。
本件では、今は治療と労災への障害補償給付の申請準備に専念し、障害補償給付の申請の結果が出た際には勤務先へ損害賠償請求するか否かを決めていくことや、集められる証拠は今のうちから集めておくことをお勧めしました。
所感・まとめ
勤務先へ損害賠償請求をするかどうかというのは悩ましい問題です。治療中の段階では、怪我が治るのか、仕事に復帰できるのか、事故前と同じような人間関係や役職で勤められるのか、などはわからない場合も多いため、迷われる方も多いようです。
後遺障害が残ってしまった場合、その後遺障害を抱えて、今後どのように生活していくかを考えていかねばなりません。本件であれば、命にもかかわりかねない事故に対して不誠実な対応をしようとした会社に今後も勤め続けるのか、ということもよく考えた方が良いでしょう。
今回ご相談者様からいただいたご質問は、実はよくいただく質問です。 労災制度や後遺障害などについて一般の方がご自身で調べて理解していくのは大変です。当事務所では、初回のご相談は無料です。労災の専門家である弁護士がお話を伺いますので、お気軽に初回無料相談をご利用ください。
この記事の監修弁護士

弁護士法人シーライト
代表弁護士 阿部 貴之
神奈川県弁護士会所属。労災事故における被害者の損害賠償問題に積極的に取り組み、人身事故の損害賠償問題について、適正な解決を目指して活動中。労働災害被害者相談の豊富な経験から、適正な後遺障害等級認定を得ることができるように的確にアドバイスし、顧客満足度も高い。
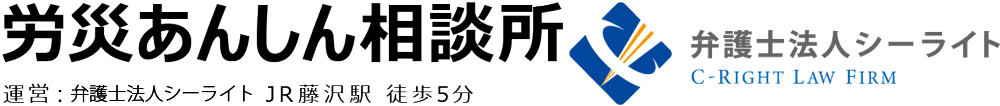
 0120-551-887
0120-551-887