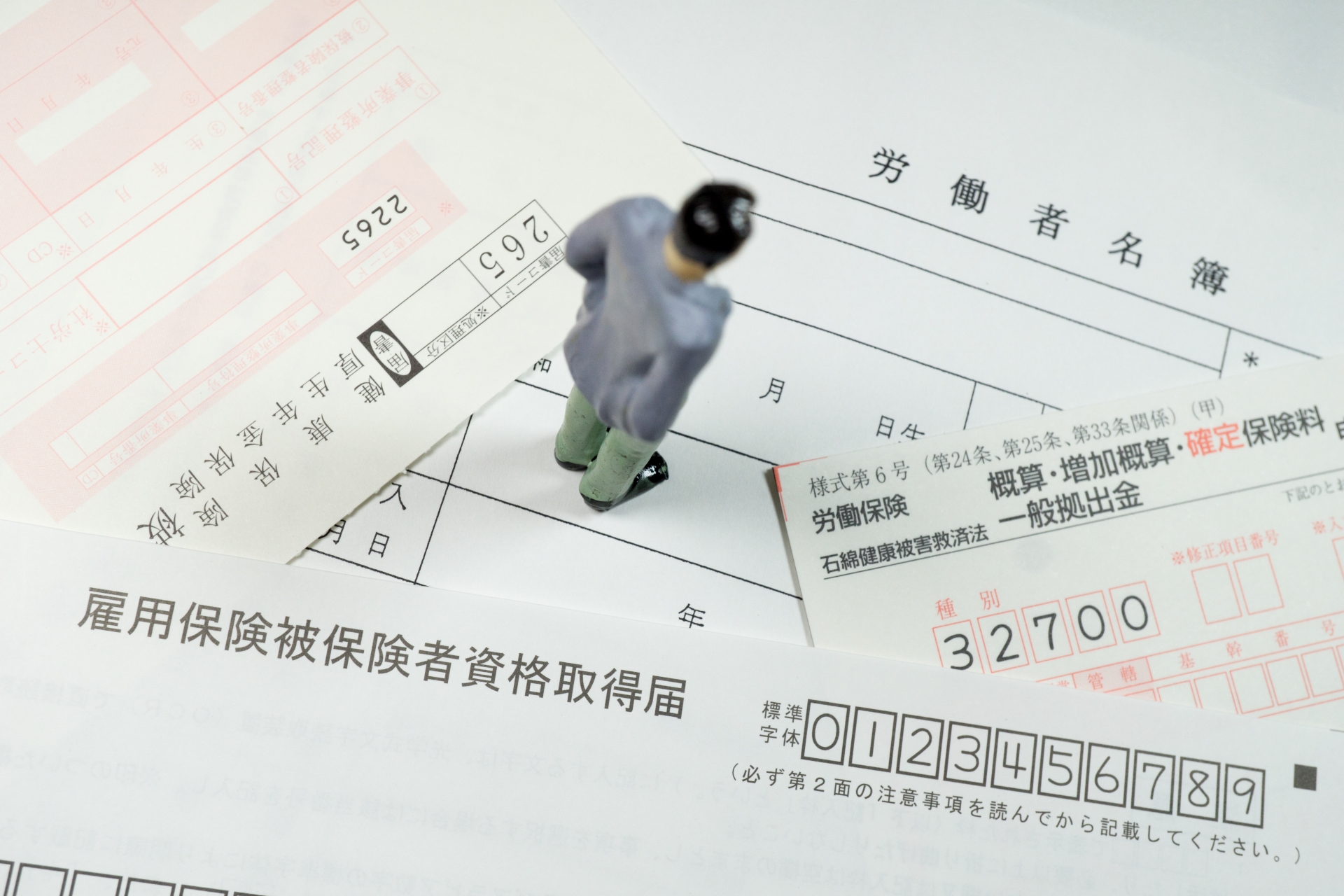労災保険は、業務中の災害や通勤中の災害によって労働者が負傷、疾病、障害または死亡した場合などに、補償を受けられる公的な制度です。しかし、事業主(会社)から退職勧奨を受け、労災保険申請前にも関わらず退職してしまった場合に労災保険が適用されるのか、不安に感じられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
労災保険が適用されるのは、事業主(会社)に在籍している人だけのものと考えている方も多いと思います。
この記事では、退職後に労災保険給付を受けることができる具体的な条件、対象となる給付の種類、手続の進め方、注意すべきポイントなどを解説します。
労災保険の仕組み
労働者災害補償保険法に基づいて、業務上の事由、複数事業労働者(※1)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷、疾病、障害もしくは死亡に対して必要な保険給付を行う制度として、労働者災害補償保険制度が設けられています。 この制度は、事業主が義務として労災保険に加入し保険料を納め、被災労働者が労災保険の給付を受けることで被災労働者の救済を図るものです。
※1 複数事業労働者とは、事業主が同一でない複数の事業に使用される労働者のことをいいます。
労災保険の特徴
- 暫定任意適用事業(※2)以外で労働者を1人でも雇用していれば事業主に加入義務がある(強制適用)
- 労働者が個別に保険料を負担する必要はない
- 事業主の過失がない場合でも、給付される
- 被災労働者に過失があった場合でも、減額はされない(例外として、労働者の故意または重過失により事故が発生した場合、給付されないことがあります)
- 物損及び慰謝料は、労災保険の補償対象外である
※2 暫定任意適用事業とは、農業、林業、水産業の事業で、常時使用労働者数が5人未満の個人経営の事業のことをいいます。
どのような労働者が対象になるのか?
事業主(会社)の指揮命令を受け、労務を提供して賃金をもらっている人は、労災保険給付の対象となります。労働者の雇用形態を問わず、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員、日雇い労働者などの非正規雇用の労働者も対象となります。
退職後でも労災保険給付の対象となる
事業主(会社)を退職後であっても、労災保険の支給要件を満たす限り、労災給付の対象になります。このことは、労働者災害補償保険法12条の5第1項にも、「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。」との規定があります。
申請前や申請中に事業主(会社)を退職した場合でも、労災保険給付の申請は可能です。労災保険の支給要件を満たしていれば、事業主(会社)を退職した後でも、労災保険を受給することができます。
では、労災保険の給付の対象となる条件についても解説します。
労災保険給付の対象となる条件
労災保険の補償を受けるためには、仕事による災害(業務災害や複数業務要因災害)または通勤災害による被災であることが条件となります。
業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害は、それぞれ災害として認められるための満たすべき要件が異なります。
業務災害について
業務災害は、「業務遂行性」と「業務起因性」の要件を満たすことが必要です。
業務遂行性とは、労働者が事業主(会社)の支配下にある状態のことをいいます。労働時間内で業務に従事している際に生じた災害である場合、原則として業務遂行性があります。
業務起因性とは、業務と負傷・疾病・死亡等との間に一定の因果関係があることをいいます。これは、仕事が原因で怪我や病気等になったという関係があるということです。
出張などで普段とは違う職場外で仕事をしている際の怪我でも、事業主の命令を受けて業務に従事している場合、原則として労災となります。他方で、私的な行為をしていた場合、労災が認められないことがあります。
複数業務要因災害について
複数業務要因災害とは、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする傷病等のことをいいます。対象となる傷病等とは、脳・心臓疾患や精神障害などです。
複数の事業場での業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価し、労災と認定できるか判断されます。
なお、1つの事業場のみの業務上の負荷で労災と認められる場合、業務災害と認定されます。
通勤災害について
通勤災害とは、通勤によって労働者が被った傷病等をいいます。
具体的には、就業に関し、次の①から③の移動を合理的な経路及び方法により行った際の、負傷、疾病、障害または、死亡を通勤災害といいます。
① 住居と就業の場所との間の往復
② 就業場所から他の就業場所への移動
③ 上記①に掲げる往復に先行し、または後続する住居間の移動
②は、複数の事業場を掛け持ちして勤務する方が、1つ目の就業場所から2つ目の就業場所に移動する場合などです。③は、帰省先住居・赴任先住居の間の移動などです。
なお、②③については、一定の要件があります。
ここで注意すべきなのは、移動中に経路を逸脱したり中断したりした場合です。
逸脱とは、通勤途中に就業や通勤と関係ない目的で通勤経路から外れてしまうことをいいます。また、中断とは、通勤経路上で、通勤と関係のない行為をすることをいいます。
例えば、事業主(会社)の帰りに映画館に入る場合、飲酒する場合です。逸脱や中断となってしまうと、逸脱や中断の間及びその後の移動は、原則として通勤災害と認められません。
ただし、通勤の途中で経路近くの公衆トイレを利用する等のささいな行為であれば、逸脱・中断とはなりません。
また、日用品の購入や病院での受診など日常生活上必要な行為の場合、逸脱や中断の例外となることがあります。逸脱や中断の例外となる場合、逸脱または中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び通勤となります。
なお、上記の通勤の要件に当てはまっていても、業務の性質を有する場合には、通勤災害ではなく業務災害となります。
このように通勤の合理的な経路や合理的な方法について十分に検討する必要があります。
労災期間の解雇制限について
労災により働くことが難しく休業することとなった場合、被災労働者が事業主(会社)から退職勧奨を受けることがあります。
しかし、被災労働者が業務災害により休業している場合、事業主(会社)が労働者を解雇することは、労働基準法19条1項によって制限されています。具体的には、業務による負傷・疾病の療養のために休業する期間およびその後30日間について、労働者を解雇することが原則として禁止されています。
そのため、退職勧奨により労働者の退職を促すような場合もあると思いますが、被災労働者が無理に同意する必要はありません。
なお、労働者の側から自身の意思で退職することは問題ありません。また、これは業務災害の場合に関する制度であり、通勤災害によって休業となった場合には適用されません。
労災で受けられる給付の種類
療養(補償)等給付
負傷・疾病の治療や、その費用の給付です。
労災指定病院にかかった際の自己負担額がゼロとなり、無料で治療を受けることができます。
労災指定病院ではない病院で労災保険適用の治療を受ける場合、治療費を一時的に自己負担し、その費用の支給を受けることができます。
休業(補償)等給付
負傷・疾病により働くことができず、賃金を受け取れない日に対する賃金の補償です。賃金の全額ではなく、一部の補償となります。
労災による傷病の療養により、労働することができないため、賃金を受けていない場合に補償を受けることができます。そのため、治療が終わっている場合や病院にあまり行っていない場合、休業補償が受けられない可能性があります。
退職後の休業についても休業補償給付を申請することはできますが、支給要件を満たす必要があります。
傷病(補償)等年金
療養を開始して1年6ヶ月を経過しても、治癒(症状固定)していない状況で、一定の障害が残っている場合に支給されます。
これは、労働基準監督署長が支給を決定し、休業(補償)給付から傷病(補償)年金に切替えが行われます。
障害(補償)等給付
負傷や疾病が治癒(症状固定)した後に一定以上の後遺障害が残った場合、障害等級に応じた給付が支払われます。
介護(補償)等給付
障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者で、一定の障害があり、家族等の介護を受けている場合に支給されます。
遺族(補償)等給付
労働災害が原因で労働者が死亡した場合、その遺族に支払われる給付です。
葬祭料等(葬祭給付)
死亡した被災労働者の葬祭に関する費用の一部を填補する目的で支給されます。
労災申請で失敗しないためのポイント!
労災申請の時効に注意
労災保険の申請は、退職後でもすることができます。しかし、労災保険の請求にも期限があり、時効を過ぎてしまうと労災保険の給付を請求する権利が消滅し、請求できなくなってしまいます。
そのため、退職後に労災申請を検討している場合には、それぞれの給付の時効に注意しましょう。
ここでは、主な補償給付の時効期間について表にまとめておきます。
| 請求内容 | 時効期間 |
| 療養(補償)等給付 | 療養の費用の支出が具体的に確定した日の翌日から2年(療養の費用の支給) |
| 休業(補償)等給付 | 労働不能のため賃金を受けない日ごとに、その翌日から2年 |
| 障害(補償)等給付 | 傷病が治癒(症状固定)した日の翌日から5年 |
| 介護(補償)等給付 | 介護を受けた月の翌月1日から2年 |
| 遺族(補償)給付 | 被災労働者が亡くなった日の翌日から5年 |
| 葬祭料・葬祭給付 | 被災労働者が亡くなった日の翌日から2年 |
証拠を確保しておく
退職後の労災の申請では、退職時点から時間が経過していることもあるため、証拠の確保が極めて重要です。 たとえば
- 業務日誌やシフト表
- 診断書やカルテ
- 同僚や上司の証言メモ
などの証拠が重要になることがあります。
労災保険の申請方法
たとえ退職後に労災保険の給付申請する場合でも、その方法については退職前後で変わりはありません。
申請の流れとしては、労働基準監督署へ申請書類の提出をします。 申請書は、所定の書式があり、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
厚生労働省のホームページ(主要様式ダウンロードコーナー)はこちら
所定の申請書は、労災保険の給付の種類ごとに用意されています。申請後は、労働基準監督署による調査が行われます。
労働基準監督署による調査が終わり、労災と認められる場合には、労災保険の支給決定がなされます。
不支給決定がなされた場合(労災と認められなかった場合)、不支給決定を争うことができます。不支給決定を争う手続は、一定の期間内に行う必要があるため、注意する必要があります。
退職後に労災保険を申請する場合に注意すべきこと
退職後でも、期限内であれば労災を申請することができます。ただし、2点、注意することがあります。
事業主(会社)に協力してもらえない可能性がある
在職している時に労災申請をする場合、事業主(会社)が申請手続に協力してくれることがあります。しかし、労災事故が発生したことを否定するなど、事業主(会社)が協力をしてくれないこともあります。
また、退職してしまうと、事業主(会社)に協力を求めにくいと感じてしまう方もいらっしゃるかと思います。
事業主(会社)から事業主証明を得られにくいケースがある
労災保険の療養補償給付や休業補償給付の申請用紙には、事業主証明欄があります。
しかし、退職後では、事業主(会社)に事業主証明欄へ記載してもらうことが依頼しづらいケースや難しいケースもあるかと思います。とくに、事業主側が労災であることを否定している場合(労災隠し)、協力を得られにくいです。
もし、事業主証明欄に事業主(会社)からの証明が得られない場合は、労働基準監督署に事情を説明して、どのように対応すればいいのかを相談します。
事業主証明がない場合でも、労災申請は可能です。事業主(会社)が協力しない場合、その事情を説明する上申書を提出する等の対応により、労災を申請します。
退職後に事業主(会社)への損害賠償請求が可能なケースも
労災について事業主(会社)の安全配慮義務違反が認められる場合、労災とは別に、損害賠償を請求することもできます。これは、退職した後でも請求することができます。
安全配慮義務とは、事業主(会社)が負う義務のひとつで、労働者の生命や健康を守るよう配慮する義務です。安全配慮義務違反であると判断される場合には、損害賠償を請求することができます。
また、安全配慮義務の他に、事業主(会社)に使用者責任が認められる場合にも、損害賠償請求をすることができます。使用者責任が認められるケースとは、他の労働者が、故意やミスによって労災事故を発生させ、それによって損害を受けた場合などです。
損害賠償請求では、労災保険ではカバーされない慰謝料なども請求することができます。
他にも、賃金補償として給付される休業(補償)給付なども満額が支給されるわけではないため、不足する部分を損害賠償として請求することができます。
ただし、労災と損害賠償とで、同じ損害への補償を二重に受け取ることはできません。そのため、労災で給付を受けた金額の一部について、損害賠償の金額から差し引いて計算されることになります。
事業主(会社)への損害賠償請求は弁護士に相談することをおすすめします
労災で受けた損害であっても、精神的苦痛に対する慰謝料などは、労災給付の対象外となります。そのため、このような損害を補償してもらうには、事業主(会社)などに対して損害賠償を請求する必要があります。
しかし、事業主(会社)が労災であることを認めないケースでは、交渉で解決することができず、訴訟などの法的手続が必要となる場合も出てきます。
労災に詳しい弁護士に相談、依頼することで、被災労働者本人の代わりに弁護士が事業主(会社)と示談交渉を行うことができます。事業主(会社)が示談交渉に応じない場合であっても、その後の訴訟へスムーズに移行することができます。
退職後であっても労災保険の申請は可能です
退職後であっても、退職した理由に関係なく、労災保険給付を受けることが可能です。「退職したからもう労災保険の受給は無理だろう」とあきらめず、ご不明点は当事務所にお尋ねください。
弁護士法人シーライトでは、労災申請サポートや事業主(会社)に対する損害賠償請求を含め、被災労働者の方のサポートをおこなっています。
労災に関してお困りのことがあれば、ご相談ください。
この記事の監修弁護士

弁護士法人シーライト
弁護士 澁谷 大
神奈川県弁護士会所属。労働災害や交通事故の相談実績多数。適正な後遺障害等級認定ができるよう、的確でわかりやすい説明に定評がある。人身損害被害の救済のために、日々努力している。
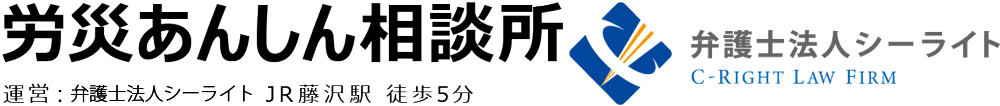
 0120-551-887
0120-551-887